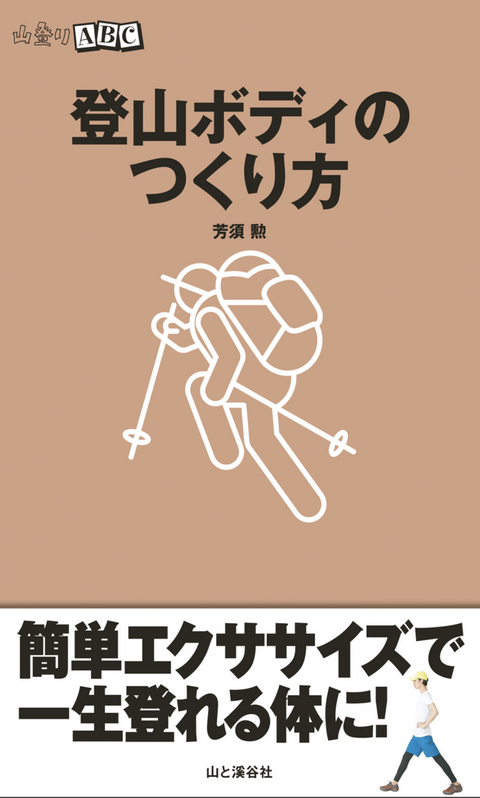ADモーリーのアウトドア書籍から学ぼう!
山登りABC 登山ボディのつくり方 / 芳須勲さん著
ADモーリーです!
まだまだアウトドア初心者のわたくしADモーリーが
様々なアウトドア書籍から、
初心者なりにこれはびっくりだな!とか、役立つぞ!
と思った知識をピックアップして載せていくこの企画。
題して、
「ADモーリーのアウトドア書籍から学ぼう!」
今週は、ポケットブックシリーズ「山登りABC」から
芳須勲さん著の
「山登りABC 登山ボディのつくり方」をピックアップ。
登山ガイド・管理栄養士・健康運動指導士の
3つの顔を持つ著者・芳須勲さんが
無理なく始められる
「登山のためのカラダづくり」の方法を
わかりやすく紹介している
「山登りABC 登山ボディのつくり方」から、
アウトドア初心者のわたくしがまず注目したのは…
「まずは階段を上ることから始めよう」
『いざ、トレーニング!と意気込んでしまうと、
なかなか続かなくなるものです。
まずは普段の生活に、
ちょっとした登山の目標を
入れるのがいいかもしれません。
富士山五合目から頂上までの高低差は約1,400mです。
駅などの階段の高さは17cmくらいですので、
およそ階段を8,235段上れば、
富士山に登ったのと同じことになります。』
(本より引用)
エスカレーターに頼りっぱなしの僕ですが、
こういった具体的な数値が出てくると
今日は階段にしてみようという考えが生まれてきそうです。
通勤・通学などで毎日のように使う階段があれば、
一度数を数えて、擬似富士登山を楽しんでみるのも
毎日の目標になって楽しいかもしれませんね!
続いて注目したのは...
「急な勾配を登る時の
足首の向きに注意」
『急勾配を登るときには、
足をまっすぐ前方に向けていると、
足首やふくらはぎに大きな負担がかかります。
登りの急勾配では、少しガニ股にすることで
足首の関節だけでなく、
ふくらはぎの筋肉の負担を少なく出来ます。
これは、下りのときに衝撃を吸収する
バネとして使う筋力を
温存させることにもつながります。』
(本より引用)
急な運動をすると身体を痛めてしまいますが、
そこには必ずと言っていいほど原因があります。
楽しかった登山の後に足首が
痛くなるのを避けるために心がけたい”教え”ですね。
やはり全体的に日頃の運動が重要な
登山ボディのつくり方になっているようです。
上で紹介した階段だけでなく、
自宅で出来る簡単なストレッチから
スラックラインを使った鍛錬方法、
そして食事から考える登山ボディの作り方など
内容満載の本になっていますので、
ぜひとも手にとってみてくださいね!
ということで、今週はここまで!
そして!
あんちゃん、この本も読んだ方が良いよ!という
マンゴー隊のみなさまからのオススメ書籍も募集します!
みなさんのレコメンドでわたくしを成長させてください。
theburn@fmyokohama.jp までお願いします!
それではまた来週ー!
- 記事一覧:最新順
- 年別: 2026年 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
- カテゴリ: お知らせ その他 リスナー投稿 釣り博士 スノーフェアリー ダッヂオーブンレシピ イベント情報 BLEU MERMAID 井手大介のカマゲンメール NO LIMIT PROJECT 今日の波情報 ネイチャーガール・コレクション サーフィン・スノーボード動画 マーメイドアルバム アウトドア看板娘 100目チャレンジ Dew写真家:豊田直之 アウトドア漫遊記 OJIと加賀谷はつみのマウンテン交換日記 深海バスターズ ザバーン登山部 マンゴーBOX 赤ワインの大漁情報 ザバーンアウトドア女子部 爆釣モーニング O2のアウトドアチャレンジ Smart Outdoor Life ADマロのアウトドアチャレンジ TEAM MANGO こいしゆうか女子キャンプ たけだBBQモテレシピ ADモーリーのアウトドアチャレンジ ADモーリーのアウトドア書籍から学ぼう! こいしゆうかのwith Camp 物欲Dモーリヤの減価償却ジャーニー