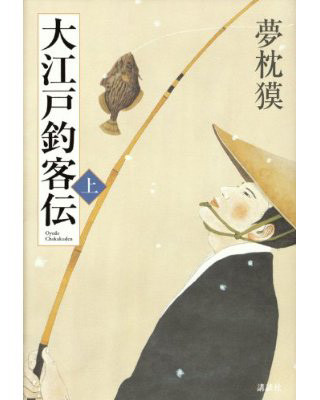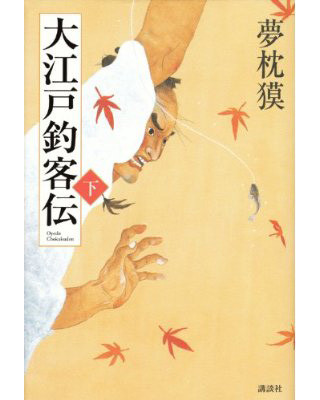夢枕獏『大江戸釣客伝』
スタッフの赤ワインです。
今日は、僕が最近出会った本を紹介させてください。
その本とは、『陰陽師』シリーズで有名な作家:夢枕獏さんの小説『大江戸釣客伝』。
子供のころにフナ釣りを始め、今でも年間70日は釣りに出るほどの釣り好き。
そんな夢枕獏さんが、「人はなぜ釣りにハマるのか」に迫った作品です。
実は、僕:赤ワイン、大の歴史小説好きでして…
この作品の紹介に歴史マニアな一面が出てしまうのをお許しください…。
この小説の主人公は、津軽采女(うねめ)。
あの弘前藩の津軽家の分家の当主で、4000石の旗本。
ちなみに、義理の父親は、忠臣蔵で有名な吉良上野介です。
彼は、小普請組と呼ばれる「役なし」の旗本で、
江戸湾でハゼやキスなどの釣りばかりを楽しむ生活でしたが、
ある時、義父の吉良上野介の力添えがあって、
将軍の側に仕える「小姓」になります。
その当時の将軍と言えば…5代将軍徳川綱吉。
そう、悪法の名高い「生類憐みの令」を出したことで犬公方と呼ばれる将軍です。
その「生類憐みの令」でついに釣りがご法度となり、
これを破ってまで釣りをしたために島流しになる人も出てきます。
そんなご時世に、主人公の津軽采女は、
日本初の釣り指南書「何羨録(かせんろく)」を書きます。
ここには、釣り場紹介から釣り道具、エサ、天候の読み方まで書かれていて、
その針の種類の豊富さを見ただけで、
江戸時代の釣り文化の豊かさが感じ取れます。
人生を変えるほどにハマッてしまう釣りの楽しさとは一体何なのか?
自分に置き換えて、自問自答してしまうような本になっています。
ちなみに、津軽采女は『何羨録』の序文に、
「 釣り人の楽しみはやはり“釣果”に尽きるだろう。
社会的名誉は重要ではない。
だが生きていくと、どうしてもなにかと煩わしい。難しいもので。
だから自分は時々、そんなことは忘れることにしている。」
と書いています。
釣り好きにはぜひ読んでいただきたい一冊です。
- 記事一覧:最新順
- 年別: 2026年 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
- カテゴリ: お知らせ その他 リスナー投稿 釣り博士 スノーフェアリー ダッヂオーブンレシピ イベント情報 BLEU MERMAID 井手大介のカマゲンメール NO LIMIT PROJECT 今日の波情報 ネイチャーガール・コレクション サーフィン・スノーボード動画 マーメイドアルバム アウトドア看板娘 100目チャレンジ Dew写真家:豊田直之 アウトドア漫遊記 OJIと加賀谷はつみのマウンテン交換日記 深海バスターズ ザバーン登山部 マンゴーBOX 赤ワインの大漁情報 ザバーンアウトドア女子部 爆釣モーニング O2のアウトドアチャレンジ Smart Outdoor Life ADマロのアウトドアチャレンジ TEAM MANGO こいしゆうか女子キャンプ たけだBBQモテレシピ ADモーリーのアウトドアチャレンジ ADモーリーのアウトドア書籍から学ぼう! こいしゆうかのwith Camp 物欲Dモーリヤの減価償却ジャーニー