
「「発達障害」と間違われる子どもたち」の著者 「子育て科学アクシス」代表で小児科医の成田奈緒子さん③

今週のゲストは、青春出版社から発売されている「「発達障害」と間違われる子どもたち」の著者、 小児科医で文教大学教授、「子育て科学アクシス」代表の成田奈緒子さんです!
成田先生は、小児科医として、発達障害をはじめとする子どもたちの脳、そして、子どもたちの発達についても研究をされています。
さらに、医療だけでなく、教育・福祉の専門家とともに子どもたちの発達について考える「子育て科学アクシス」を主宰され、同時に、発達障害者支援センターや児童相談所での嘱託医、精神心理疾患外来の医師を担当され、大学では特別支援教育を志す学生への指導もされていらっしゃいます。
そんな成田先生が、今年、お書きになったのが、青春出版社から発売されています「「発達障害」と間違われる子どもたち」です。3月に発売されベストセラーになっています。
昨日は、「脳には育つ順番がある」というお話でした。
今夜は脳を育てていくうえでとっても大切な「生活を整える」について伺いました!
原始的な脳「体の脳」の働きがバランスを崩してしまうと、発達障害と間違われるようないろんな症候が出やすくなるそうです。もし、そういうことがあった場合でも、まず生活を整えるという事を心がけるだけで、びっくりするほど子どもの様子が変わっていくことを、成田先生は実際にたくさん見てきたんだそうです。
もし5歳を過ぎているけれども、なんだかうまくいかないなぁというお子さんを見た場合に、何歳であっても、まず手を付けるのは「体の脳」を育て直すと、成田先生たちは言っているんだそうです。
そのためには、夜遅くまでゲームして起きているとか、遊んじゃうとか、あるいは塾に行っているとかで、夜遅くまで起きる習慣がついているようなお子さんの場合、急に「早く寝なさい」って親御さんが言っても、お布団の中に入っても寝付けなかったりする。なので、成田先生たちがアドバイスするのは、「朝早く起きる事から頑張って始めましょう、太陽が昇る時刻に起きていただきたいです。それだけです。」と伝えているんだそうです。
朝早く起きれない子の場合、幼児であれば、親御さんが抱っこして、ベランダなどに出て太陽の光を浴びさせちゃうというのが、一番目は覚めやすいんだそうです。
そこで、お子さんの好きな食べ物や動画などを用意して、「楽しいね」と言ってあげれば、幼い子であれば1週間で本当に変わってくるそうです。
人間は昼行性の動物なので、そもそも朝一番に元気になるようないろいろなホルモンとか、セロトニンという脳内物質が大量に分泌されるように元々セットされているんだそうです。その分泌を日の光を浴びて順調に出してあげて、「朝は爽快なんだ」「楽しいんだ」というのを実感させてあげると、自分の体の中がうまく働いているという気持ちになってくるので、朝ごはんも食べられるし、今日も一日頑張れるという気持ちになることができ、子どもの方からこれを続けてみたいとなることがとても多いんだそうです。
朝日が昇ってくる時間帯・地域によって違いますが、一般的に朝6時頃が、セロトニンが分泌されやすい時刻になるので、その時刻を起床時刻にしていただくのを推奨しているそうです。小学生や中学生でも朝食をとり時間とか排便の時間とか見越して、学校行くまでの1時間なり1時間半の時間がとることが出来るので、基本的には6時起床を目指してくださいと、もっと出来る人は5時半とか5時に起床して、朝に勉強をするような時間を持ってくると、脳は寝た後というのが一番すっきりした状態なので、本当は学習効果も朝が一番いいんだそうです。
成田先生も、ずーっと朝勉強で、大学受験まで塾に行かず勉強されてきたそうで、自分で実践してきてよかったことを進めているだけだとお話されていました。
そうなると‥気になるのが睡眠時間。
成田先生曰く「大人は、8時間とるのは難しいので、とれる日は7時間とるようにお願いしています。23時までに就寝、6時までに起床。
子どもだと、5歳で11時間の睡眠が最低でも欲しいところなんですが、今の日本だと難しいので10時間をお願いしています。夜8時までに寝て、朝6時までに起きる。小学生だと、本当だったら10時間が理想なんですが、9時間として9時に就寝、6時に起床。中高生だと、夜10時に就寝、朝6時に起床が理想的になります。朝、起きるという事を根性入れてしばらくやってねと、言っています。最初は寝不足で昼に眠くなっちゃうので、昼寝をしないように保育士さんや親御さんが頑張って、夜眠くなったら、早めにお布団に入るっていうのを、5歳くらいまでだと1週間、小学生くらいだと1か月くらい。で、中高生くらいになると3か月くらい頑張ると身についてきます。なので、そこまではちょっと根性がいるんですけれども、でも、やった子たちは、体の中がすっきりしてきている事とか、朝食欲がわいて朝食を食べることができるようと、実感することが出来きます。先日も、朝ごはんをパクパク食べてきました、という高校生がいました。朝、吐き気がするとか、頭痛がする、お腹が痛いなどの症状を訴える、いわゆる起立性調節障害と言われる子どもたちも、ものすごく増えているんですが、私たちは、それを生活改善でほとんどの場合、よくしています。」と。
まだまだヒントがたくさあるようなので、続きは明日、伺っていきます!
詳しくは、成田先生の著書、青春出版社から発売されている「「発達障害」と間違われる子どもたち」をぜひ読んでみてください。
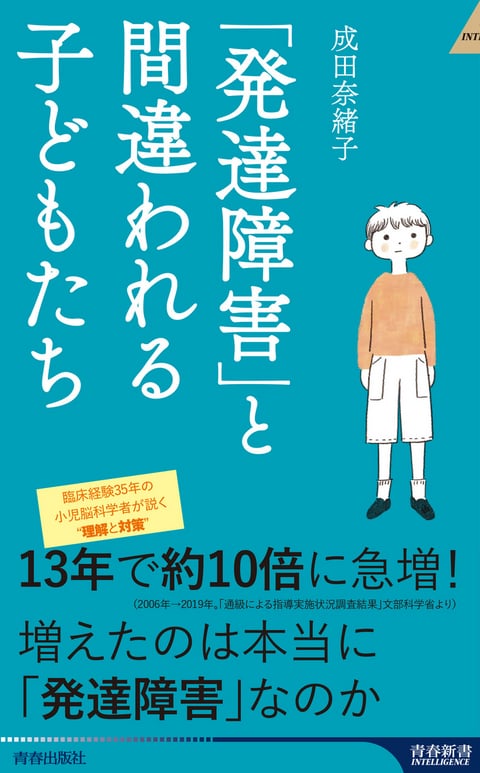
「発達障害」と間違われる子どもたち /成田奈緒子 青春出版社