
「「発達障害」と間違われる子どもたち」の著者 「子育て科学アクシス」代表で小児科医の成田奈緒子さん②

今週は、青春出版社から発売されている「「発達障害」と間違われる子どもたち」の著者、 小児科医で文教大学教授、「子育て科学アクシス」代表の成田奈緒子さんです!
成田先生は、小児科医として、発達障害をはじめとする子どもたちの脳、そして、子どもたちの発達についても研究をされています。
さらに、医療だけでなく、教育・福祉の専門家とともに子どもたちの発達について考える「子育て科学アクシス」を主宰され、同時に、発達障害者支援センターや児童相談所での嘱託医、精神心理疾患外来の医師を担当され、大学では特別支援教育を志す学生への指導もされていらっしゃいます。
そんな成田先生が、今年、お書きになったのが、青春出版社から発売されています「「発達障害」と間違われる子どもたち」です。3月に発売されてから、すでに10版を超えるベストセラーになっています。
今夜は「脳が育つ順番」について伺いました!
小児科の医師である成田先生曰く、
「「発達 ≒脳の育ち」。もちろん、体が大きくなるという事も発達の言葉の意味には含まれるのですが、それ以外のほとんどの部分は「脳が順番にバランスよく育つ」という風に発達の事を理解していただくといいと思います。その順番の中で最も大切なのが、生まれてから5年間、大体幼稚園、保育園を卒業する時期ぐらいまでに育ちあがる「体の脳」と私たちは呼んでいますが、「原始的な脳」、いわゆる動物たちも持っているな基礎的な部分をつかさどる脳、具体的に言うと、寝る事とか、起きる事とか、お腹がすいてご飯が食べたくなるとか、それから呼吸とか、心臓が動くとか、本当に生きるために必要なことを全部やってくれる脳の部分が、まず最初に育ちます。
脳の中に時計が組み込まれていて、これによって、誰にも起こされなくても目が覚める、誰に言われなくても眠くなるという脳を作るという事になります。それが出来ると誰に言われなくてもお腹が空いたという感覚、つまり食欲がわいて、ちゃんと一日3回きっちりご飯が食べられるようになる。これ、当たり前のように思えるのですが、生まれたての赤ちゃんというのは、寝たり起きたりを日中も繰り返していて、夜は寝て朝は起きるというリズムができていないんですね。で、ミルクとかも3時間毎にダラダラと飲んでいるだけで、一日3回食事をするという規則はできていないですよね。これはまだ脳が育っていないからで、ここから大人がきちんと刺激を入れてあげることで、「太陽が登った、朝だ」って脳がわかって勝手に目が覚める。そして、太陽が沈んで暗くなってくると「夜だ、寝なきゃ」って勝手に眠くなるっていう脳を作ること、これが「体の脳を作る」ということになります。
で、次にそれを追いかけるように「お利口さんの脳」と私たちは呼んでいますが、これが一般にイメージする脳で、しわしわでめちゃくちゃ大きい大脳新皮質という部分が「お利口さんの脳」。いわゆる言葉が喋れたり、字が書けたりとか、ボールを蹴ったらサッカーゴールに入るとか、そういう人間ならではの能力、そういったものが詰まっているというのが「お利口さんの脳」となります。なので、どうしても一般の方からすると「お利口さん脳」の育ちが、脳の育ちと思いがちなのですが、あくまでも「体の脳」が最初になります。ちなみに子どもは大体1歳を過ぎたころから言葉をしゃべり始めたりとか、あるいはストローでジュースを飲んだりとか、スプーン持ったりとかしだすので、大体「お利口さん脳」というのは1歳を過ぎたころから育ち始めます。あくまでその生まれてから1歳までに「体の脳」が育った上に「お利口さん脳」が育っていくというイメージ。おうちに例えると一階部分が「体の脳」でその上に二階が乗っかっていくというイメージになりますので、あくまでも一階部分を頑丈に育てましょうという事になります。
そして最後に「心の脳」と私たちは呼んでますが、この原始的な「体の脳」で動物と同じ脳ですから、喜怒哀楽とか「食べたい!」とか「寝たい!」とか欲望が起こるんですが、人間・・そう寝たいからすぐに寝られるわけでなく、食べたいからと言って食べられるわけでもなく、周りの人の状況とか自分が置かれている社会の環境とかによって、それをどうするか考えないといけないんですが、「心の脳」では、それを考えて今どうするのかな‥って決めるのが出来るようになる「前頭葉」という「お利口さん脳」の中でも最も高度な部分を使って判断する脳ということで、これが出来てやっと脳の発達が完成するということになります。
大事なのは「心の脳」がいつ育つのかというと、10歳を過ぎてから、小学校4年生を過ぎてからになります。なので、あまりこの順番を間違えて親御さんが2歳とか3歳の子に、「ちゃんと自分で考えて行動しなさい」とか、「言うとおりにしなさい」とか「みんなの迷惑を考えて行動しなさい」とか言いすぎちゃうと、ちょっとバランスが崩れちゃうということがあり得る、ということになります。」
では、「脳のバランスを崩す」というのは、どういった事なのでしょうか?
「「体の脳」は寝る事、起きる事、食べる事が自律的にできるということなのですが、これが出来るよりも前に「お利口さん脳」を頑丈に育てようと、例えば習い事を割と小さいうちからやったりとか、サッカーとかスポーツ教室とかにたくさん行かせたりすると、どうしても寝る時間が短くなったりとかで、悪気はないんだけれども一階部分はすごくやせ細った・・「体の脳」は、やせ細った頑丈ではない状態、その一方で2階部分は頑丈にできてしまった・・家をイメージしてもらうと、なんかアンバランスでちょっとした地震が来たら崩れそうだなっていう家のイメージです。なので、こういうアンバランスな脳を作ってしまうと、「ちっちゃいけど賢そう」みたいにはなるんですけれども、ちょっとお友達にいじめられたとか、ちょっと何か失敗しちゃったということが、震度2くらいの地震というイメージですね、ガタガタ・・ってバランスを崩してしまって、思わぬ心身症状が出てしまったりすることが割とあります。
早期教育を否定するつもりはありませんが、あくまで「体の脳」を頑丈に作った上で・・寝ること、起きる事、食べる事をしっかりさせた上で、プラスαと捉えていただければいいなと思います。」
成田先生の本には「脳は何歳になっても育ち続ける」とも書かれています。
「脳の細胞の数は生まれた時に決まっているのですが、休んでいる細胞がたくさんあるので、その細胞を刺激して繋げてあげるといくらでも育ちます。ただし、土台の「体の脳」が頑丈にできていないと脳のバランスが崩れてしまって、うまく育たなくなってしまうので、あくまで一番最初の脳を頑丈にしておけば、何歳からでも育ちます。理想的には5歳までに「体の脳」を頑丈に育てておけばもう大丈夫・・なんですけれども、「あー。しまった5歳すぎちゃったのに、全然育ってない・・」でも、大丈夫です。もし脳を育て直さないといけないなと思われた方は、まず早起きから始める・・だけです。」
早起き!というキーワードが出てきたところで、続きは、明日、詳しく伺っていきます!
さらに詳しいお話は、青春出版社から発売されている「「発達障害」と間違われる子どもたち」で!
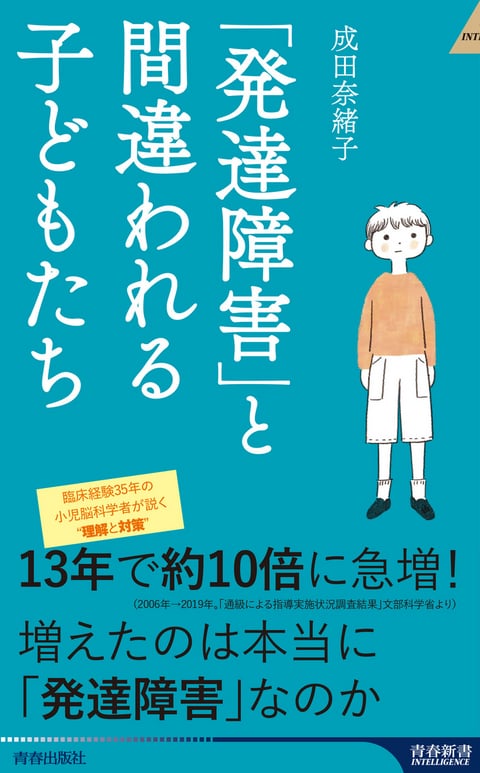
「発達障害」と間違われる子どもたち /成田奈緒子 青春出版社