
服から始める、サステナブルな暮らし「CO+」代表 才野英里子さん④
今週は、サステナブルライフスタイルブランド CO+代表の才野英里子さんにお話を伺いました。
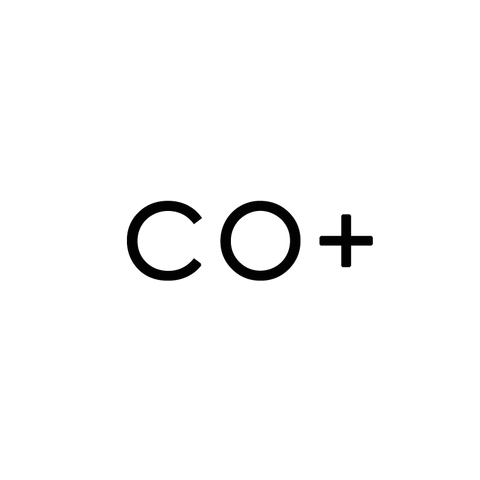
CO+では
・環境に配慮して服を作ること。
・労働者・生産者に配慮し、働く人たちを傷つけずに服を作ること。
・お客様との壁をなくしてブランドを運営すること。
という、「3つの約束」を掲げています。
これまでは、お客さんが得られる情報が限られていて、服がどこで作られ、どんな素材を使い、その素材はどこから来たのか見えないことが普通でした。才野さんは「見えないことで問題が起きているため、その部分を見えるようにしなければいけない」と考え、可能な限り素材、工場などの情報を伝えることで、お客様との間の透明性を大事にしています。
インドの工場探しはコロナ禍に入ってから行ったそう。現地に直接行けない中での選定基準は第三者機関からの認証。GOTS認証、フェアトレード認証を取っていて、欧米のサステナブルブランドの生産も行っているなど、外部からの信用が基準になったと言います。

インドの村では、女の子は学校に行っていても農業優先で休むことがあったり、児童連れ去りで連れ去られた子どもがコットン農場で労働を強いられることが今も多く行われているという現状があります。服作りにおいて労働環境が一番大事と、児童労働や、毒性の強い薬剤が使われていない、人権・社会的に配慮されていることも農場を選ぶ基準になっています。
インドの社会的、経済的に弱い立場にある人に対して雇用で貢献したいと同時に、サステナビリティを大事にしたいと思うと、雇用に繋げるにはたくさん売る必要があるが、大量生産は廃棄に繋がってしまう矛盾があり、どう折り合いをつけるかが難しいと現状の課題についてもお話しくださいました。
才野さんは京都大学大学院地球環境学課程を修了。大学では文学部だったものの、モンゴルで出会った方々と話すうちに国際協力に興味を持ち、大学院で環境政策を学ぶことを選んだとか。その経験が雇用と、サステナビリティの両立という部分に繋がっています。
またCO+では、購入時のこだわりも。
公式サイトで購入すると、配送にかかるCO2のカーボンオフセットする仕組みに参加。ショップカードは、東北コットンプロジェクトで出来たコットンから作られた紙を使用しています。
(東北コットンプロジェクト:東日本大震災で塩害に遭った土地で、塩に強いコットンを植えて土壌を再生する取り組み)
梱包は、段ボールはリサイクル率96%以上の循環型の素材であることから段ボールのメール便にこだわっています。
今後、CO+で目指しているのは、プロダクトとしては「ずっと着られるデザインのシンプルなもの」。また透明性にこだわり、コットン農場から縫製工場まで実際に訪れ、どう作っているかを理解して見ている方に伝えるようにしていきたいとおっしゃっていました。
☆CO+
☆Instagram
☆Twitter
☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!
番組への感想もお待ちしています。