
2021年6月9日(水)SDGs Quest みらい甲子園・ 桐蔭学園高等学校・GISゼミ①
「SDGs Quest みらい甲子園 神奈川県大会 2020」の
全94チームの中から、ベスト10に選ばれた学生の皆さんをご紹介しています。
今回初めて開催された「SDGs Quest みらい甲子園 神奈川県大会」は、
高校生が持続可能な地球の未来を考え行動するために、SDGsを探究し、
社会課題解決に向けたアイデアを考える機会を創発し、そのアクションアイデアを発表・表彰する大会。
今日は、「東京海上日動賞」を受賞した桐蔭学園高等学校・GISゼミの
稲田拓実さん、相馬悠星さんにお話を伺います。
まさかこんな素晴らしい賞を受賞できるとは!と語ってくれた2人をはじめとするGISゼミのメンバーが提案したアクションアイデアは「みんなのBOSAIプラン3.0」
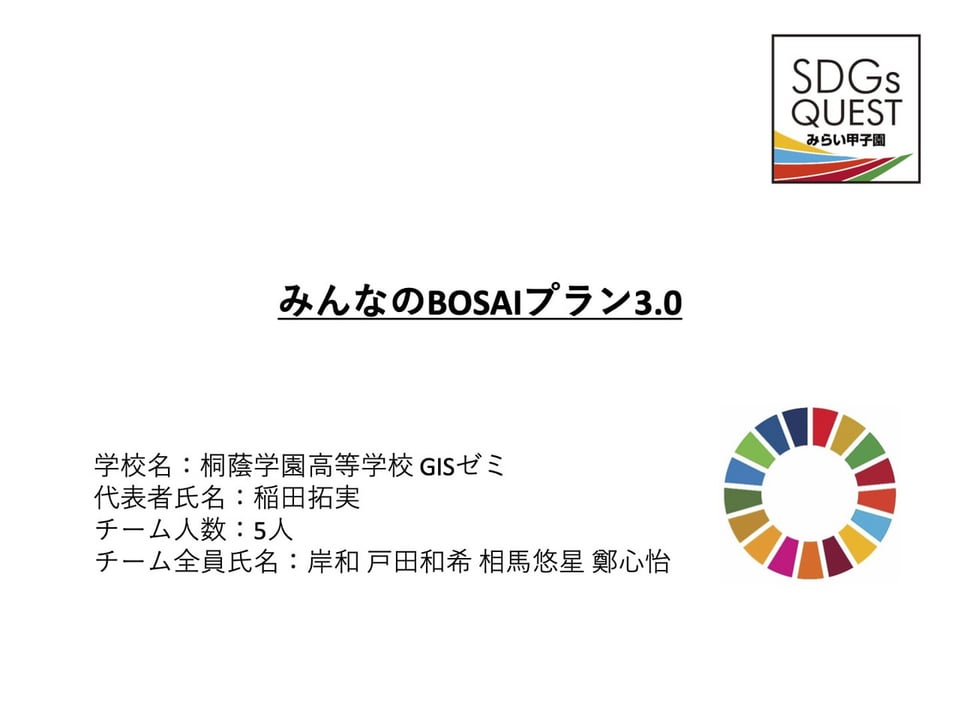
このアイデアは、10年前の東日本大震災がきっかけ。震災で悲しむ人を一人でも減らしたいという思いから、「高校生の僕たちにできることはなんだろう?」と考え学校の防災教育を変えることで何か力になれるのではと思ったのだそうです。
様々な専門家に協力や、文献調査やフィールドワークを通して防災授業のモデルプランを作り、色々な場で実践して磨き上げていくというプロジェクトになっています。具体的には、防災教育に映像コンテンツ、ロールプレイングゲーム、ICT教材の三本柱を立て、この3つを通していかに生徒に興味を持って学んでもらえるかということを大事に組み立てていきました。防災教育はどうしても「重い、つまらない」という思いが先行してしまう。その中でもそれほど防災に関心のない人たちに学んでもらえるかと意識して進めてきたと言います。
映像コンテンツはリアリティと緊張感のあるシミュレーションができると考え、
被害者の証言、実際に起きた際のシミュレーションもとてもリアルで緊張感を持たせることができるのではないかとNHKの「東日本大震災アーカイブス」を使用。
ロールプレイングゲームには、一つのお題に対して自分たちの最適解を話し合って決める「クロスロード」というカードゲームを使用。これは自分たち生徒が実際にその状況に立った時にどういった行動をすればいいのかを話し合う内容になっています。
最後のICT教材は、GISゼミのGIS、地理情報システムのこと。スマートフォンでただの地図だけでなく土地の高さなどのデータを重ねることによって視覚的に見てわかりやすい。その特徴を生かして、自分たちが住んでいる所はどんな災害に遭いやすいのだろうと考え、バーチャルで避難訓練を行います。学校から家までどういう避難経路で帰れるのかを通して、主体的にスマートフォンを使って学びを深めたいと考えています。
アイデアのタイトルの「3.0」という数字は、「ソサエティ5.0」という政府が進めている未来に向けた取り組みをオマージュしたもの。
1.0はこれまでの一方的な訓練や授業、2.0は事前に日時がわかっている避難訓練。いつどこで起きるかわからない災害に向けて少しずつでもやっていけないかということで、1.0、2.0を踏まえた次のステージに行きたいということで名付けられました。
明日も桐蔭学園高等学校・GISゼミのお話をお届けします。
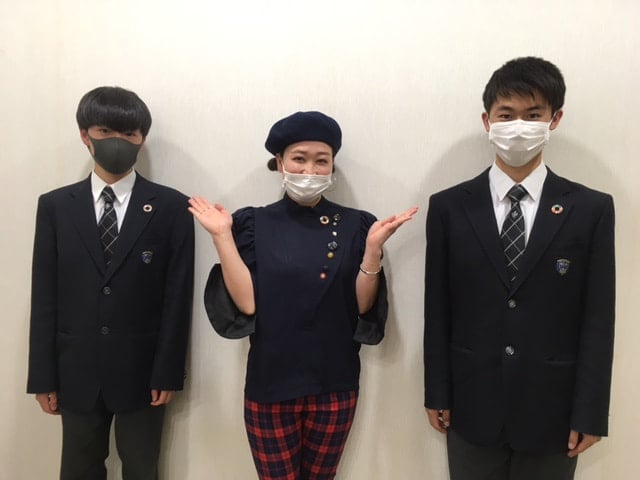
☆桐蔭学園高等学校
3月27日の大会の様子は、YouTubeで見ることができます。
☆SDGs QUEST みらい甲子園
☆「あなたのサステナブルなこと」も番組に教えてください!
感想や、あなたの周りのSDGsな取り組みなどご紹介する予定です。