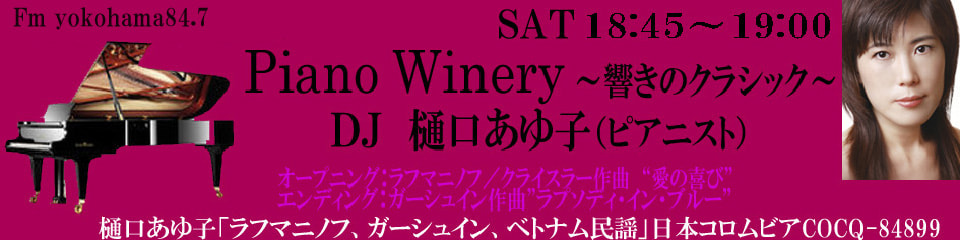
萩谷康一さんの初めてのラジオ フルートレッスン
今週は、2曲の名曲、フォーレ(Gabriel Fauré)の「パヴァーヌ」と、ビゼー( Georges Bizet )の「アルルの女のメヌエット」の共通点についてお話しくださいました。
本来、オーケストラのために書かれた曲ですが、あまりにも美しい曲のために、フルートとピアノにアレンジされたものがよく演奏されています。2曲とも古い舞曲を用いた作品です。それぞれの作品が書かれた14年間の間に、フランスの作風がどのように変化をしていったのか、そのようなことにも注目をしてみてください。
1886年 Pavanue 「パヴァーヌ」/ ガブリエル・フォーレ(Gabriel Fauré)
1872年 L’arlesienne 「アルルの女のメヌエット」/ ジョルジュ・ビゼー( Georges Bizet )
= = =
🎼 パヴァーヌ(Pavane):
16世紀のルネサンス(Renaissance)の時代にスペイン起源のゆったりとした2拍子の踊りです。
後に、ロマン派のフォーレや、近代音楽派のラヴェルによって、管弦楽曲として復活しました。ラヴェル(Ravel)の「亡き王女のためのパヴァーヌ」(Pavane pour une infante défunte G-Dur)もとても有名です。2人の作曲家が書いたパヴァーヌは、共に甘美で崇高、そして清楚なイメージで作曲されています。
= =
🎼 メヌエット(仏: Menuet ムニュエ/ 伊:Minuetto / 独: Menuett )
17世紀のバロック(Baroque) 時代に、フランスの宮廷で流行した優雅な3拍子の踊りです。組曲の中の1曲として作曲され、バッハ(J .S .Bach)もたくさんメヌエットを書きました。
後に、古典派の時代には、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンが室内楽や交響曲の中の一つの楽章として作曲しています。
= =
🎵 『アルルの女』( L'Arlésienne)」について:
戯曲は、アルフォンス・ドーデ(Alphonse Daudet)の短編小説「風車小屋だより」の中の同名作品を原作にしています。戯曲の上演にあたり1872年、ビゼーは全27曲の付随音楽を作曲しました。その中から4曲を選び編曲し、これが「アルルの女」の第1組曲と呼ばれています。そしてビゼーの死後、友人のエルネスト・ギロー (Ernest Guiraud) により第2組曲が完成されました。この3曲目がメヌエットで、今日では「アルルの女のメヌエット」として広く知られ、フルートの大切なレパートリーとなっています。力強い中間部を挟み、優雅な趣のあるメロディーがフルートで奏でられています。
= = =
番組へのメッセージ、フルートのご質問などもお待ちしております!
↓

写真: 萩谷康一さん、 吉川由利子さん