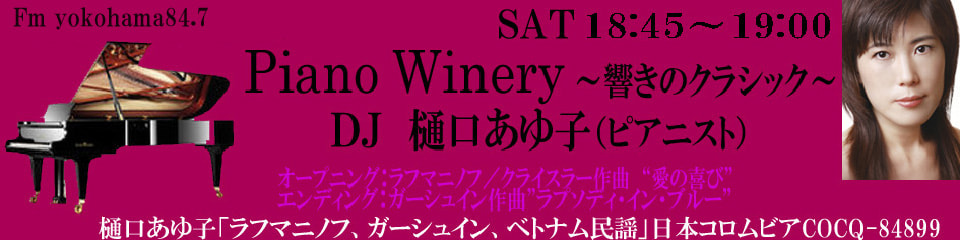
萩谷康一さんの初めてのラジオ フルートレッスン
今週は、ヘンデルが活躍したバロック音楽の時代(17世紀~18世紀の中頃)には、現代とは異なる独特な楽譜の書き方があったというお話でした。
萩谷康一さんと吉川由利子さんによる演奏:
ヘンデルのフルート・ソナタト長調 HWV363

写真: 萩谷康一さん、吉川由利子さん
= = =
🎼 バロック音楽の時代の楽譜:
楽譜はメモ書きのような感じで、正確な設計図のようなものではありませんでした。スラー、スタッカート、テヌートなど、音と音を区切ったり、つなげたりすることで、音楽に表情を付ける記号の指示はほとんど省かれていました。装飾も最低限度で、演奏者が即興的に加えていました。しかし楽譜通りに演奏しても、それはそれでとても綺麗で大作曲家ならではの美しがあります。
= = =
🪈ヘンデルの楽曲を演奏するとき:
楽譜に表情を加えて演奏することになります。経験を積んだ演奏者なら、色々表現を加えて演奏したくなるのではないでしょうか。
そこで、お手本にお勧めしたいのが
⬇️
⚫︎ゲオルク・フィリップ・テレマンの 入門ソナタ集
Georg Philipp Telemann
Methodische Sonaten
= =
⚫︎クヴァンツ、ヨハン・ヨアヒム のフルート演奏試論
Quantz, Johann Joachim
VERSUCH EINER ANWEISUNG DIE FLOTE TRAVERSIERE ZU SPIELEN
= =
⚫︎またCDやネットで検索し、気に入った楽曲をコピーして練習してみるのも良いかと思います。
= = =
🪈 萩谷先生のアドバイス:
まずは、何も付け加えていないオリジナルのメロディーを練習し、把握してから装飾(オーナメンテーション/ornamentation )を試みた方が良いかと思います。演奏者のセンスがうかがえるので、上手に取り入れると一層華やかな演奏になると思います。皆さんもご自身のセンスを生かして素敵な装飾を考えてみてください!