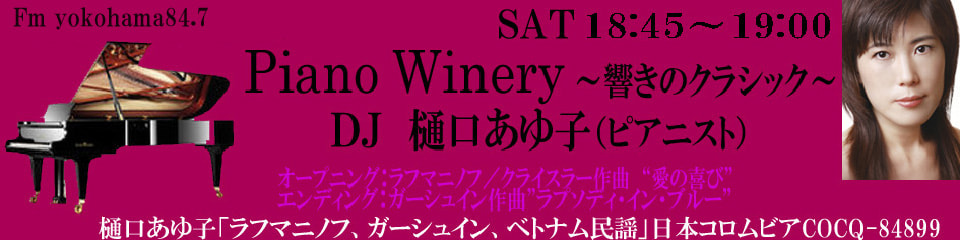
東 誠三さんの演奏で~
🔹1曲目:
モーリス・ラヴェル
組曲 「クープランの墓」よりメヌエット
ピアノ: 東 誠三さん Seizo Azuma, piano
使用楽器:Steinway & Sons / Takagi Klavier
Maurice Ravel (1875-1937)
Le Tombeau de Couperin
No. 3. Menuet
= =
🎼 クープランとは:
フランスのバロック時代(1600年代)における大作曲家・フランソワ・クープラン(François Couperin)で、大クープラン (Couperin le Grand)として知られています。
「クープランの墓」というタイトルは、作曲家・クープランの石碑が建っている墓という意味ではありません。フランス特有の言い回しがあり、芸術作品など過去の偉大な人物に対して敬意を表し、「捧げる」という言葉を使う風習があります。意訳すると「クープランに捧ぐ」という意味のタイトルになります。
= =
🎼 もう一つの「クープランの墓」の意味:
ラヴェルの母が亡くなった時期と重なり、その時代は第一次世界大戦が勃発した時期でした。ラヴェルは志願兵として従軍しました。このひとつひとつの曲は、戦死した親しい友人のために捧げられています。「クープランの墓」は、ラヴェルが最後に作曲したピアノ独奏曲です。
= =
🎼 6つの組曲:
ラヴェルは、色々な情景を描くことに長けていましたが、この組曲のひとつひとつの曲に限っては、決まった情景を描くことはありません。古い時代の優雅な典雅な踊りを中心としたスタイルで書かれていて、それが最大の特徴となっています。
楽曲「クープランの墓」は、組曲と言って6つの小さな曲が集まって出来ています。
「クープランの墓」
第1曲 前奏曲 No. 1. Prelude
第2曲 フーガ No. 2. Fugue
第3曲 フォルラーヌ No. 3. Forlane
第4曲 リゴードン No. 4. Rigaudon
第5曲 メヌエット No. 5. Menuet
第6曲 トッカータ No. 6. Toccata
*フォルラーヌ、リゴードン、メヌエットは、フランスにとてもゆかりのある深い踊りです。
*メヌエット: 前回のおさらい
17世紀後半から18世紀にかけて、緩やかな三拍子の主にフランスの宮廷でよく踊られていた踊りのための音楽です。ヴェルサイユ宮殿を建てた太陽王、ルイ14世(Louis XIV)は、メヌエットを宮廷舞踊に取り入れ、特に好んで踊っていました。
後に、踊る目的から器楽の中の組曲として、バッハ、ヘンデルなどが、そして後にはソナタの1楽章としてハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなどが盛んにこの形式で曲を書きました。
= = =
🔹エンディング~
ジャック・ルヴィエ(Jacques Rouvier)のアルバムより
モーリス・ラヴェル
組曲 「クープランの墓」より
トッカータ No. 6. Toccata
ピアノ:ジャック・ルヴィエ Jacques Rouvier, piano
Maurice Ravel
Le Tombeau de Couperin
No. 6. Toccata
= = =
東先生より
5/10、5/18に開催した「ラヴェル生誕150周年記念 ラヴェル・ピアノ曲連続演奏会」を無事に終演いたしました。多くのお客様にお越し頂きありがとうございました。また沢山のご支援をいただき、感謝いたします。ラヴェルの曲をこれだけまとめて聴いたことはなかったという声をたくさんいただきました。
ピアノ愛好家のための雑誌、「月刊ショパン」での連載コラムも引き続きお楽しみください!
