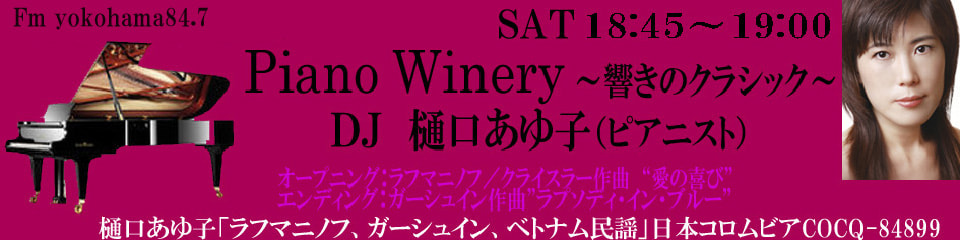
萩谷康一さんの初めてのラジオ フルートレッスン
今週は前回に引き続き、組曲(英語: suite)について解説していただきました。
組曲(suite)は、いくつかの舞曲の小品や楽章をまとめてバランスよく連ね、一つの作品としたものです。
先月は、1.アルマンド Ⅱ. クーラント III. サラバンド
今月は、IV.ガヴォット V.ジーグ について。
= = =
<古典組曲と近代組曲の違い>
⚫︎古典組曲(バロック音楽時代 1600~1750年ごろ):
いろいろな舞曲の集まりです。古典組曲の標準的な配列(楽章構成)は、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、メヌエット、ジーグというように大まかに順番が決まっています。
⚫︎近代組曲(19世紀後半~):
いくつかの曲と自由に組み合わせています。古典組曲とは異なり、より自由な形式で様々な性格の楽曲を組み合わせることができます。
= =
<古典組曲・バロック時代の形式>
🎼 ガヴォット gavotte:
17世紀に広まったフランス発祥の古い舞曲。語源は「アルプスの山に住む人」でアルプス地方に由来します。中庸のテンポの舞曲で、4分の4拍子、2分の2拍子。特色は、小節の半ばや、アウフタクトから始まり、明るく軽快。
*アウフタクト:
楽曲やフレーズが弱拍から始まる。ドイツ語の「Auftakt」をカタカナ表記したもので、日本語では「弱起」とも呼ばれます。
= =
🎼 ジーグ gigue(英/仏):
ジグという踊りが起源の舞曲で、スコットランドやアイルランドをはじめとする、イギリス起源だと言われています。通常は組曲を締めくくる役割で最後に置かれます。速いテンポ、軽快なリズムが特徴。構成は、イタリア式とフランス式があります。
*イタリア式:8分の6拍子、8分の9拍子、8分の12拍子。速いテンポ。単純明快。
*フランス式:リズムやアクセントが複雑。追いかけるように展開するフーガ的形式。
語源の一つは、フランス語で、はしゃぐを意味するgiguer、また中世の古いドイツ語で、ヴァイオリンを意味するgīga。(現在のドイツ語でもヴァイオリンを意味するGeigeに派生し、今でも使われています。)
= = =

写真: 萩谷康一さん、吉川由利子さん
= = =
番組へのメッセージ、フルートのご質問などもお待ちしております!
↓