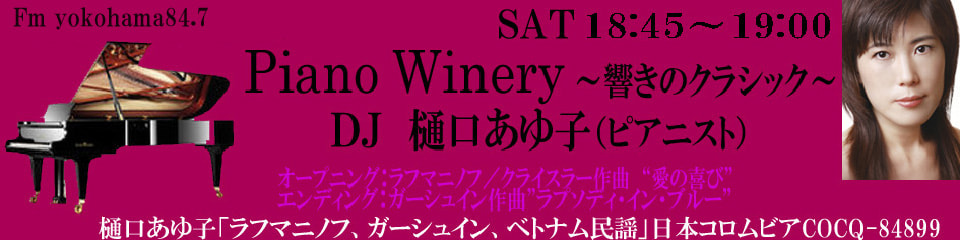
萩谷康一さんの初めてのラジオ フルートレッスン
今週は、「印象派の音楽」についてお話しいただきました。
一般的に印象派というと絵画を思い浮かべますが、音楽にも印象派はあり、最初の印象派の作曲家はクロード・ドビュッシー(Claude Achille Debussy)。そして、印象派の芸術家はなんとジャポニズム(英: Japonism・仏:Japonisme)に影響を受けていたというお話は驚きましたね!
= = =
<絵画における印象派>
「印象派の絵画」では、クロード・モネ(Clude Monet)の1872年の作品、「印象・日の出」(Impression, soleil levant)が印象派という呼称のきっかけとなりました。印象派の絵画は、物の印象を捉えて描いたパステル調の絵画で、絵画における伝統的な手法や主題から脱却し、自然をより直接的かつ感情豊かに描写しました。
= = =
<音楽における印象派>
♪印象派以前はロマン派
喜怒哀楽の感情が盛り込まれた写実的な表現が主流。
⬇️
♪印象派
ドビュッシーがはじめた印象派は、メロディーは非連続的で断片的。色彩のイメージを感じさせる和音を使うなど絵画のように色の変化を重視する方向に転換。それ以降、演奏は色を出す工夫が求められました。
= = =
<文学における象徴派>との繋がり
📕 文学には印象派と呼ばれるものはないのですが、象徴派(symbolistes)といい、人間の内面のような本来は目に見えないものを、目に見えるものに置き換えて表現したのが特徴です。
ステファヌ・マラルメ(Stéphane Mallarmé)
シャルル=ピエール・ボードレール(Charles-Pierre Baudelaire)
ポール・マリー・ヴェルレーヌ(Paul Marie Verlaine)
アルチュール・ランボー(Arthur Rimbaud)
19世紀末のパリでは、象徴派の詩人たちが台頭し、ドビュッシーもパリのカフェやマラルメのサロンなどで象徴派の詩人たちと交流し、大きな影響を受けました。
= = =
🪈 萩谷さんがドイツで学んだこと!
19世紀以降の曲を演奏するときは、どの先生からも「そのフレーズでは色を変えて!色を出して!別の色で!」などと指導をされたそうです。そして、オーレル・ニコレ(Aurèle Nicolet)先生からは、「金魚の動きで!」と言われたそうです。解釈は、「豊かな尻尾の金魚がスーッと向きを変えて泳ぐゴージャスな様子を演奏してみてください!」
🎻ヴァイオリンや🎹ピアノとは違い、🪈フルートで音の色を変えるということはとても難しいことですが、プリミティブな音の原理のフルートならではの特徴を生かして、やり方は多様ですが、努力してみてください! ~萩谷先生のお言葉~
= = =
番組へのメッセージ、フルートのご質問などもお待ちしております!
↓

写真:萩谷康一さん、吉川由利子さん