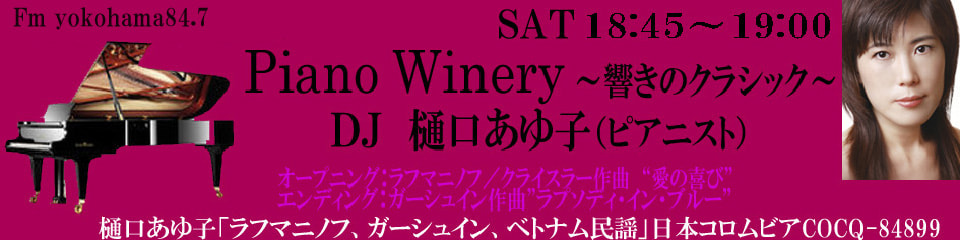
第10回 ピアニスト 東 誠三さんの “スペシャル・クラシック・サロン”
本日は、東京藝術大学教授・ピアニスト 東 誠三さんによる「スペシャル・クラシック・サロン」をお楽しみいただきました。
第10回目は、フランスの作曲家・ドビュッシー「月の光」について。
東 誠三さんの演奏とドビュッシーについて, 時代背景を交えながら解説をしていただきました。
Debussy,Claude Achille
Suite bergamasque
III. "Clair de lune”

写真:ピアニスト 東 誠三さん
= = =
ピアニスト 東 誠三さん
Seizo Azuma, piano
<プロフィール>
1962年生まれ。神奈川県在住。東京音楽大学付属高校から東京音楽大学へ進み、井口愛子氏、中島和彦氏、野島稔氏、片岡ハルコ氏に師事。1983年、大学在学中に第52回日本音楽コンクール第1位。その後、フランス政府給費留学生としてパリ国立高等音楽学院に留学。日本国際、モントリオール(カナダ)、カサドシュ(アメリカ)など、数多くの国際音楽コンクールで優勝・入賞。これまでに、ヨーロッパ、北米などでリサイタル、オーケストラと共演し、国内ではN響をはじめ、各地の主要オーケストラにソリストとして招かれている。 1998年、第24回ショパン協会賞を受賞。
ソロ活動と共に室内楽にも強い意欲を示し、「ボアヴェール・トリオ」での活動をはじめ、多くのトップソリスト達と絶妙なコラボレーションを聴かせている。 2008年より2012年にかけて、全8回のベートーヴェン・ピアノソナタ全曲演奏会を福島県三春交流館「まほら」にて好評開催。2012年には、ジュネーブ国際音楽コンクール・ピアノ部門の審査員を務めた。
CDは「ベートーヴェン:悲愴&告別ソナタ」、「ラ・カンパネラ~リスト名曲集」、ベートーヴェン・ピアノ・ソナタ全曲演奏会シリーズのライブ録音全9集など、これまでに多数リリース。いずれも高い評価を受けている。現在、活発な演奏活動と共に、東京藝術大学教授、東京音楽大学客員教授、スズキ・メソード特別講師として後進の指導も行っている。また、近年では日本音楽コンクールをはじめ、数々のコンクールの審査を務めるほか、フランスの「MuicaAlp」夏期音楽アカデミー&フェスティバルに招かれている。
日本ショパン協会 理事。
= = =
🎼 フランスの作曲家・ドビュッシー「月の光」について:
「月の光」は、単独でも有名ですがベルガマスク組曲の第3曲目の曲です。
フランスの詩人、ポール・ヴェルレーヌ Paul Verlaine (1844-1896) の詩集、艶なる宴(Fêtes galantes)にインスピレーションを受けました。
= = =
🎼 その時代のパリ:
ドイツとの戦争が終わり、世の中の混乱が終息して産業が発達していった時期でした。それに伴って、パリの街がどんどん整備されました。例えば、エッフェル塔が建てられたり、 パリにある老舗のひとつで世界初の百貨店ともいわれている「Le Bon Marché (ル・ボン・マルシェ)」も開店しました。そして色々な工業製品が街中に溢れ、活気があって華やかな時代でした。
この時代をベル・エポック(仏: Belle Époque:「美しい時代」)と呼んでいます。ベル・エポックとはフランス語で「美しき時代」または「古き良き時代」と訳され、19世紀末から20世紀初頭にかけてのフランス文化が繁栄した時代を指します。 この時代は伝統的な良さと現代的な発想が融合するヨーロッパの歴史上でも最も魅力的な時代でした。
= = =
🎼 東 誠三さんにとってのドビュッシー:
「素晴らしい作品を書いた作曲家は数多くいます。例えば、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(Johann Sebastian Bach)、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト( Wolfgang Amadeus Mozart)、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)など。
私にとって、ドビュッシーは、このような作曲家に匹敵するような大切な作曲家です。」
= = =
🎼 ドビュッシーの作品の特徴:
「それまで誰もが表現しようとしなかった内容の表現を独特の感性や感覚を駆使して音として組み立てていったことにあります。非常に斬新な発想によって、それまで誰もが作り得なかった響きを作っていき、そしてその感情だけでなく、自然の現象から得られる印象とか、人間の心の中の言葉に出来ない闇の広がりのようなことまで表現した作曲家です。私は彼のピアノ曲も大好きですし、彼が書いた歌や、色々な編成の室内楽の曲なども大好きで、よく聴いたり演奏したりしています。」
♪ ♪ ♪
番組へのメッセージ、リクエスト、フルートのご質問などもお待ちしております!
↓