
滝ともはるの横浜の夜は眠らない2018年11月5日
今回のゲストは、玉城ちはるさんでした。

女性目線による餃子愛の詰った餃子店ガイドブック+α『餃子女子』の著書でお馴染みですが
本職は歌手ですとおっしゃる玉城ちはるさんも参加していて頂いた番組名物「クイズ横浜」おさらいです。
番組をお聴きになった方、聴いてないよというみなさんも御一緒にお考え下さい
答えはこのコラムの後
(これであなたも横浜通)
江戸時代、洗濯は大変な仕事でした。
一般庶民は肌着以外は毎日同じ物を着ていて上着の洗濯は月に数回、肌着も週1~2回洗濯する程度だったそうです。
クイズ横浜第1問
もう一度言いますとにかく着物の洗濯は大変でした。
何故大変かというとその洗濯方法でした。
そのまま水につけると縮んでしまうし、よれよれになるからです。
江戸時代、着物の洗濯はどうやっていたのでしょうか?
ヒント
石鹸もアイロンもない時代です。ほとんど作り直すような作業ですね
脇沢金次郎さんという人が横浜の「清水屋」というクリーニング店を大きく発展させました。
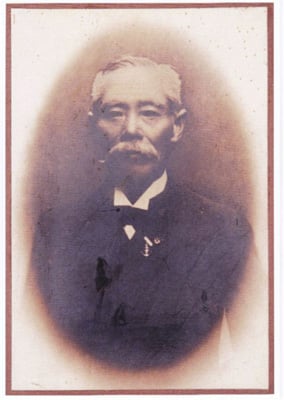
クイズ横浜第2問
清水屋が信用を得るようになったきっかけはある事件でした。
慶応2年、関内の大火事で横浜市内全域が大被害をこうむりました。
その時に金次郎さんはあることをして客から預かった洋服が被害にあうことを防ぎ、外国人の信用を獲得しました。
さて金次郎さんは預かった洋服をどうしたのでしょうか?
ヒント
クリーニング店はきれいな地下水が出るところに作られていました。
クリーニング屋とはいえ明治初期の洗濯は「ソーダ水」と石鹸で衣服を濡らして
板や石段にたたきつけるという素朴な方法でした。

クイズ横浜第3問
電気アイロンが日本で普及したのは大正時代でした。
しかしアイロンは明治時代に外国からやってきました。
電気でないとしたら、さてどんなアイロンだったでしょうか?
ヒント
煙突がついていました
第1問答え
「着物を一度ほどき、バラバラにして板に張り付けて乾かし、乾いたら再び縫った」そうです。
第2問答え
「預かった洋服を井戸に投げ込んだ。」
ほとんどの家財動画を焼失した外国人は衣服が無事に戻ったのに驚き「清水屋」に依頼が殺到したそうです。
第3問答え
「炭火アイロン」
文字通り炭をアイロンの形をして鉄製の器に入れて、その熱で洋服のしわを伸ばしたそうです。
さて、さてみなさんは何問お解りでしたでしょうか?
This program is brought to you by CERTE.
月曜日の深夜は『横浜の夜は眠らない』をお聴き逃しなく♪
お聴き逃しの方は、次回の放送開始まで「radiko.jp」で視聴可能です。
http://radiko.jp/
パラダイスカフェ
TEL: 045-228-1668
HP: http://www.paradisecafe2001.com/
今後のライブ一覧
http://www.paradisecafe2001.com/liveschedule